「もっと自信をつけさせたい」
「自信を持ってプレーしたら、もっと上手くなるのに」
「でも、自信をどうやってつけさせればいいんだろう…」
そんなふうに悩んだことはありませんか?
私自身、コーチをしていて何度も同じ壁にぶつかりました。
選手に自信があれば一気に成長できるのに、その自信がなかなか育たない。
どう声をかければいいのか、どう導けばいいのか、迷う瞬間が必ずあります。
でも、本物の自信は「与える」ことはできません。
むしろ与えようと焦るほど、逆に選手から自信を奪ってしまうこともあるのです。
この記事では、「選手に自信をつけさせたい」と悩むコーチに向けて、奪わずに、そして自分で育てていけるよう励ます関わり方 をお伝えします。
自信は“与える”ものではない
「自信」とは単なる思い込みではなく、積み重ねた努力や経験に裏打ちされた確信です。
小さな成功と失敗の経験を繰り返す中で、「自分ならできる」という確信が育ちます。
トップアスリートの自信も魔法のように生まれたわけではありません。
何千回もの練習、数えきれない挑戦と失敗。
その裏付けがあるからこそ、大舞台でも揺るがない自信を持てます。
だからコーチの役割は、「自信を与える」ことではなく、選手が自信を育める環境をつくることにあります。
コーチが自信を奪ってしまう場面
一生懸命のつもりでも、コーチの関わり方次第で選手の自信は簡単に崩れてしまいます。
たとえば――
- ミスを恐れさせる指導
コーチが「なんでそんなミスを…」など失敗にばかり注目させてしまうと、選手が自分自身に「自分はダメだ」というレッテルを貼ってしまいます。
小さな失敗のたびに刷り込まれれば、挑戦する意欲はしぼみ、自信を積み上げる機会が奪われます。 - 挑戦を脅威に変えてしまう雰囲気
失敗を許さない空気の中では、挑戦は“学び”ではなく“リスク”になります。
安心感がなければ、選手は安全策ばかり選び、成長のチャンスを逃してしまいます。 - 愛情や信頼を示さない態度
失敗したときに冷たく突き放されると、選手は「自分は見放された」と感じます。
「言わなくてもわかるだろう」では信頼は伝わりません。
言葉や態度で示さなければ、次のチャレンジに踏み出す勇気は奪われてしまいます。 - コーチ自身のイライラ
機嫌をコントロールできないと、怒鳴ったり強い言葉を使ってしまいます。
選手は顔色を伺いながら練習することになり、集中できません。
少しずつ積み上げるはずの成功体験が途切れ、自信を育てる土壌が奪われてしまいます。
これらはすべて「自信を奪う」関わり方。
気づかないうちに、選手の可能性を削ってしまいます。
コーチが自信をつけさせるためにできること
「つけさせる」とあえて書きましたが、正しくは「選手が自分でつけていけるように励ます」ことです。コーチができる関わりを整理すると、次の3つになります。
1.信じて待つ
まずは、信じて待っていることを言葉で伝えることが大切です。
- 「いつ伸びるかはわからない。だからこそ、みんな成長できると思ってる」
- 「自分で次のステップへ登っていくことで自信がついていく。こつこつ頑張ろう」
コーチに信じてもらえているとわかるだけで、選手は安心して挑戦できます。
2.よい問いかけをする
「なんで?」という質問は、説明を求めているつもりでも、選手には詰問のように響くことがあります。
代わりに、次のステップを見えるようにする問いかけをしましょう。
- 「どうしたかった?」
- 「次はどうすればいい?」
「なぜできない?」はコーチが頭で考える問い。
「どうやったらうまくいく?」は選手と一緒に考えられる問いです。
3.成長のプロセスを共有する
選手が「どうしたい」と表現できた場面を見つけたら、すぐに共有しましょう。
- 親指を立てて「見てたよ」と合図を送る
- うなずくだけでも「認めてもらえた」と感じられる
小さな合図や言葉が、選手に「自分は前に進んでいる」という感覚を残します。
ほめることに頼りすぎない
選手に自信をつけさせたいと考えるとき、「とにかくほめること」に頼ってしまうケースが多くあります。
もちろん、ほめられて嬉しい経験は選手を前向きにし、必要な場面もあります。
しかし、コーチがずっと横でほめ続けることはできません。
試合でも練習でも、選手を常に見ていられるわけではありません。
カテゴリーが上がれば、ほめられる機会は減っていきます。
もし「ほめられること=自信」になってしまったら、
ほめられなくなった瞬間から、自信は下がってしまうのです。
私自身、シーズンを通して「ほめるコーチング」にトライしたことがあります。
しかし終盤には「ほめられるために行動する」選手ばかりになってしまいました。
バスケットを純粋に楽しむよりも、ほめられたいからバスケットをするようになりました。
だからこそ大切なのは、選手が自分で自信を育てていくプロセスを応援すること。
ほめることに頼らず、努力や挑戦を通して「自分で自信をつけられる力」を育むのが、コーチの大きな役割です。
まとめ
選手に自信を「与える」ことはできません。
でも、コーチの関わりひとつで自信を「奪ってしまう」ことはあります。
だからこそ大切なのは、奪わず、励まし、育てる関わり方です。
信じて待ち、問いかけで導き、成長を共有し、ほめることに依存させない。
その環境の中で、選手は「自分の力を信じる」ことを学び、やがて本物の自信を手に入れていきます。
それこそが、コーチにだからこそできる最高のサポートです。
関連書籍
※本の商品リンクにはアフィリエイトを利用しています。
※読んでくださる方にとってプラスになる、かつさらに学びを深めたい方向けに選書しています。
『マインドセット』(キャロル・S・ドゥエック)
挑戦や失敗を“脅威”ではなく“学び”と捉える「成長マインドセット」の考え方は、自信を育む基盤になります。
『インナーゲーム』(W・ティモシー・ガルウェイ)
コーチの声かけや環境が、選手の「心の声」をどう変えるかを学べる一冊。自分を信じる力を伸ばすための視点が得られます。
『GRIT』(アンジェラ・ダックワース)
才能よりも「やり抜く力」が成果を生むことを示した名著。困難を乗り越える経験が、自信につながることを教えてくれます。
関連記事
- 保護者との関係に悩むコーチへ:親と“協力関係”を築く3つのポイント
保護者との関係に悩むのは、どのコーチも通る道です。
衝突を避け、チーム全体を前向きに導くためのヒントを紹介します。 - 失敗を恐れない!選手の成長を促すコーチング法:失敗から学ぶ成功率アップのための秘訣
失敗を恐れると挑戦は止まります。
選手が安心してトライできる雰囲気づくりと、失敗を成長に変える指導のコツをまとめました。 - 『嫌われる勇気』に学ぶ|「ほめられない…」と悩む指導者が楽になる2つの視点
「もっとほめなきゃ」と苦しくなっていませんか?
『嫌われる勇気』から学ぶ、ほめに頼らず自信を育てるための視点を紹介します。
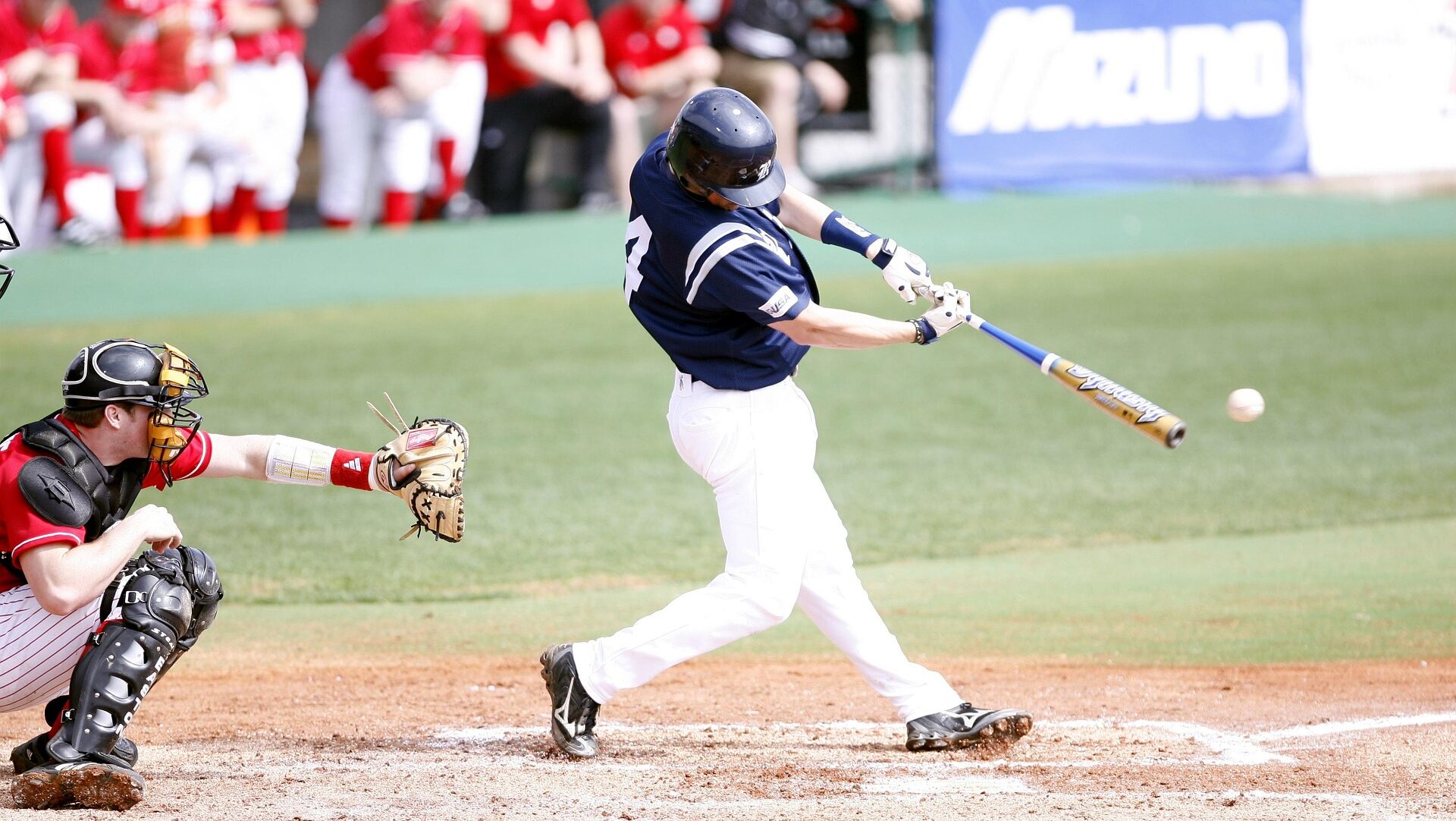


コメント