「一生懸命やっているのに、なかなか伸びてこない…」
コーチをしていると、そんな選手に出会うことがあります。
練習には休まず参加している。
指示されたことも一生懸命こなしている。
けれど、なぜか上達のスピードが遅い。
努力をしているのは間違いないので、強く指導することもできない。
かといって、このままでは選手自身の努力も「報われない努力」になってしまう。
選手もコーチも、頑張っていること自体に満足してしまう。
そんなとき、コーチはどう関わっていけばいいんだろう?
答えの一つが「挑戦の習慣」です。
頑張ることと挑戦することは似ているようで違います。
「頑張っているからOK」から抜け出して
「ノーチャレンジはダメ」「失敗は成長の証」という基準を持つことが、
“頑張ってるのに伸びない選手”を大きく変えていきます。
頑張ってるのに伸びない選手の特徴
「努力しているのに伸びない選手」にはいくつかの共通点があります。
- 練習を“こなす”努力になっている
→ 与えられたメニューは一生懸命やるが、自分から工夫や挑戦をしない。 - 失敗を避け、安全なプレーばかり選んでしまう
→ ミスしたくない気持ちが前面に出て、すでにできていることにこだわる。 - がむしゃらに一生懸命だけど、変化や成長が見えにくい
→ 練習量は多いのに、質的な変化が起こっていない。
こうした姿はコーチにとって明らかにさぼっている選手に対してアプローチしていくのとは違い、「確かに頑張っているから、そのまま様子を見るか」という判断につながります。
しかし、長い目で見ても「努力を否定できないのに、変化が起こらない」という状況に陥ります。
挑戦の習慣とは?
ここで大事なのが「挑戦の習慣」です。
「努力を否定できないのに、変化が起こらない」場面に遭遇したら、すぐさま選手たちに伝えます。
- “ノーチャレンジはダメ”
失敗はあっていい。挑戦しないと上達しない。
自分のコンフォートゾーンから自分で出てこよう。 - 失敗は成長の必須条件
ミスやうまくいかない経験を通してしか、本当の上達は生まれない。
成功からだけではなく、失敗からも学べるようになろう。 - 学校とスポーツの違い
学校は「正解を教えてもらえる場」。
スポーツは「正解を自分で探す場」「正解を自分たちで作る場」。
だから、自分のプレーに責任を持ち、自分で改善を続ける挑戦が欠かせない。
つまり、「挑戦の習慣」とは、
自分で自分を成長させる姿勢を、日常の中で当たり前にすることです。
まずは仲間がいる状態で、みんなでチャレンジする姿勢を身につけていく。
そこから、一人でも挑戦していけるようになっていきます。
挑戦の習慣を考えるときに思い出すのが、サッカー漫画『アオアシ』(小林有吾・小学館)です。
主人公・アシトは、何度も失敗し、伸び悩みながらも「挑戦をやめない」ことで成長していきます。
指導者や仲間の関わり方もリアルで、コーチ目線で読んでも多くの学びがあります。
※本の商品リンクには、アフィリエイトを利用しています。
※選手やコーチが「挑戦する意味」を考えるきっかけになる作品です。
コーチができる支援
「挑戦の習慣」を身につけさせるには、コーチの工夫が大きな鍵を握ります。
- 小さな挑戦課題を与える
例:「〇本連続でシュートを決めよう」
「今日のトレーニングのランメニュー3本は切れないけど、1本目は絶対切ろう」 - 挑戦したかどうかを評価する
結果ではなく「挑戦の過程」を見て認める。
→ 「それはいい失敗!」(あのミスは挑戦した証拠だ!)
→ 「今日は何にチャレンジする?」 - 挑戦を讃える文化を作る
選手同士で「いいチャレンジ!」と声をかけ合えるように雰囲気を育てる。
コーチが「挑戦を見ているよ」と伝えるだけで、選手の目の輝きが変わります。
チャレンジャーであり続ける選手を育てる
スポーツに「達成」というゴールはありません。
プロ選手でさえ常に課題と向き合い、改善を繰り返しています。
だからこそ、選手には「チャレンジャーであり続ける姿勢」が必要です。
失敗を認め、そこから改善する挑戦を繰り返すこと。
それこそが、結果よりも価値のある習慣です。
そして、その習慣を選手に根づかせるのは、コーチの大切な役割です。
まとめ
- 「頑張ってるのに伸びない」選手は、努力が“挑戦”になっていない
- 成長を引き出すには「挑戦の習慣」をつけていくことが大切
- コーチは「失敗はOK、ノーチャレンジはNG」という基準を示し、挑戦する文化をつくる
頑張っているだけ、こなしているだけの練習ではなく、努力を“挑戦”に変える。
何かにチャレンジできる選手の目は、好奇心であふれています。
その一歩をコーチが後押しできれば、選手はチャレンジャーであり続け、自ら成長を進める存在になっていきます。
関連書籍
今回の記事テーマ「挑戦の習慣」を深めて考えるなら、次の本もおすすめです。
『アオアシ』(小林有吾・小学館)
主人公・アシトが何度も失敗しながらも挑戦をやめず、成長していく物語。遂に完結を迎えました。
コーチの視点で読んでも「挑戦を促す声かけ」のヒントが多く、育成年代の指導にもつながります。
『静学スタイル』(井田勝通・カンゼン)
静岡学園サッカー部の指導哲学をまとめた一冊。
選手が自分で考え、挑戦し、失敗を乗り越える文化をどうつくるか。今回のテーマに直結する実践例です。
※本の商品リンクにはアフィリエイトを利用しています。
※記事の内容に共感した方がさらに深く学べる本を選んで紹介しています。
挑戦を支える関連記事
努力しているのに伸びないチーム|挑戦を習慣化する文化をつくる
選手は努力しているのにチームとしては停滞してしまう…。
そんなときに必要なのが「挑戦を文化にする視点」。コーチ自身の関わり方から解説します。
選手の“やる気がない”はエネルギー不足?e-tankで心を満たすチームづくり
選手が挑戦できない背景には、エネルギー切れが隠れていることも。
心の“タンク”を満たす仕組みづくりが、挑戦する力を支えます。
失敗を恐れない!選手の成長を促すコーチング法:失敗から学ぶ成功率アップのための秘訣
挑戦と失敗は切り離せません。
失敗を恐れない環境をつくることで、選手は安心して新しい挑戦に踏み出せます。
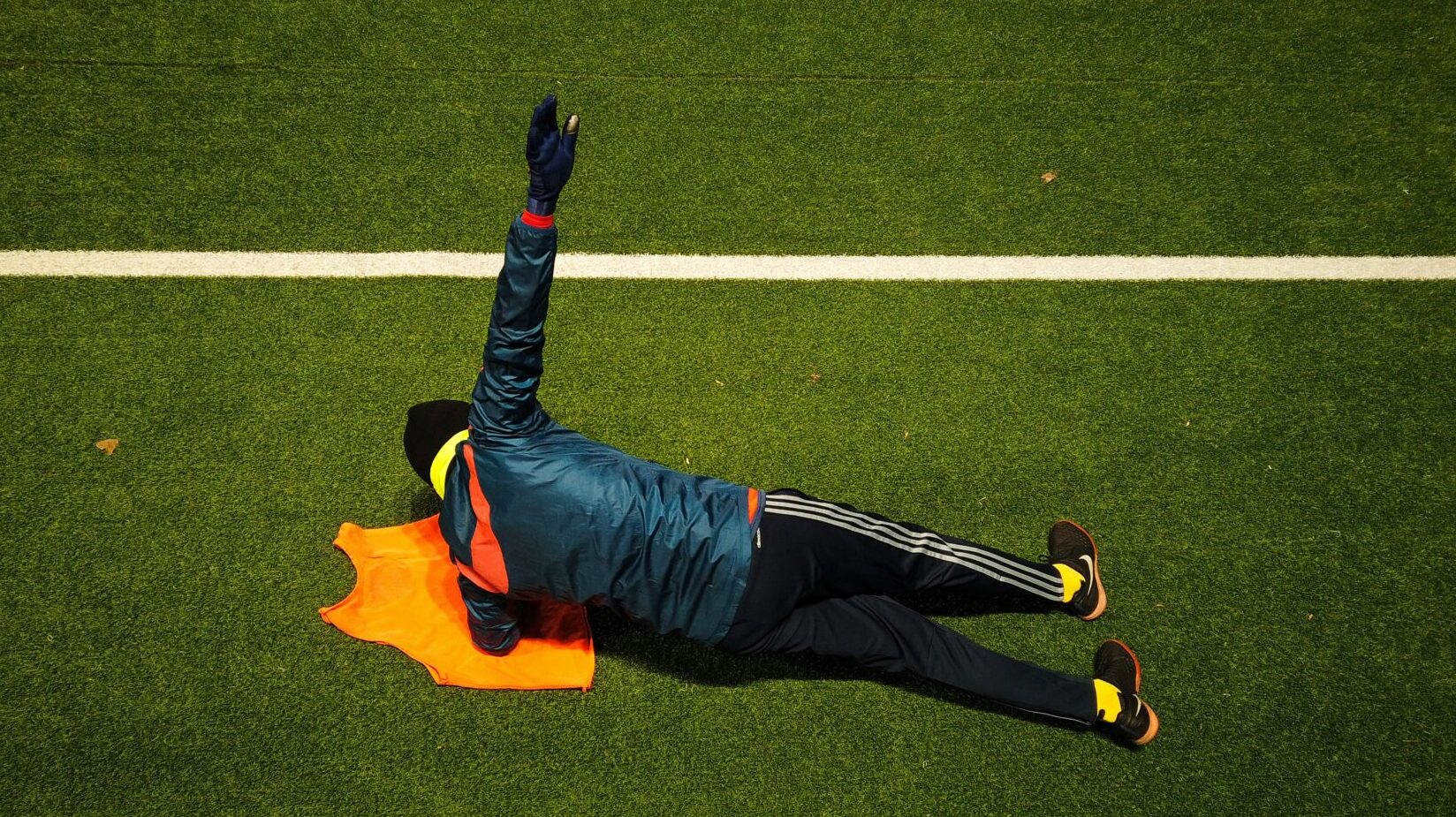


コメント